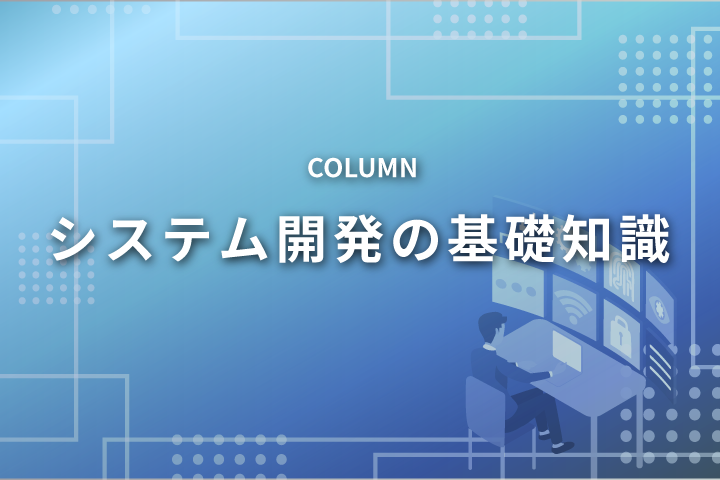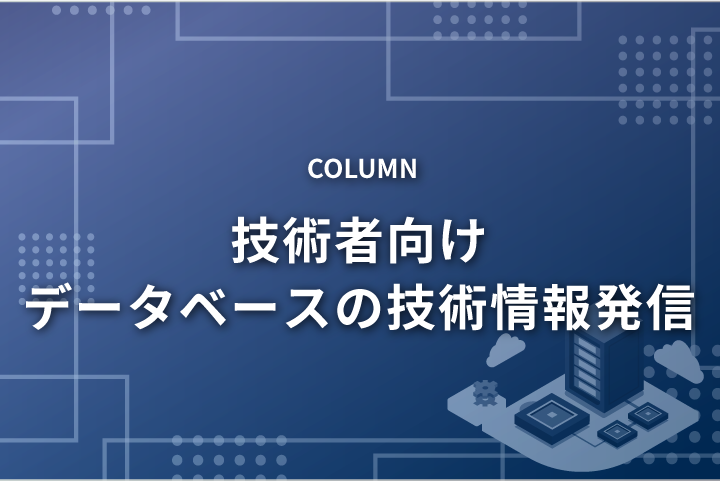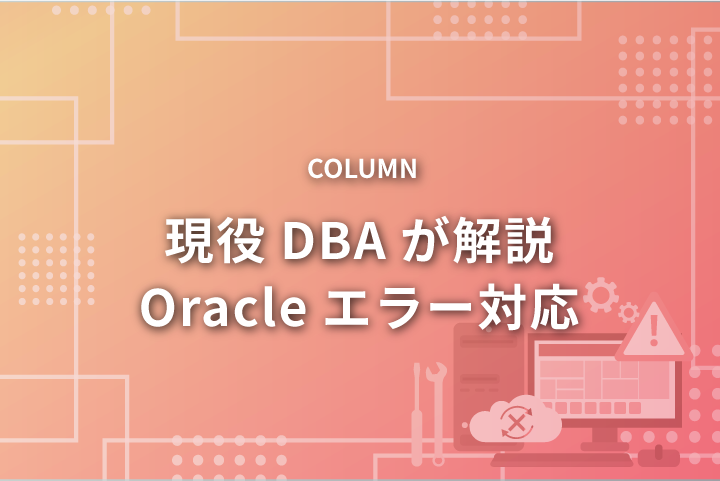第3回:予算管理とクラウドサービスの親和性
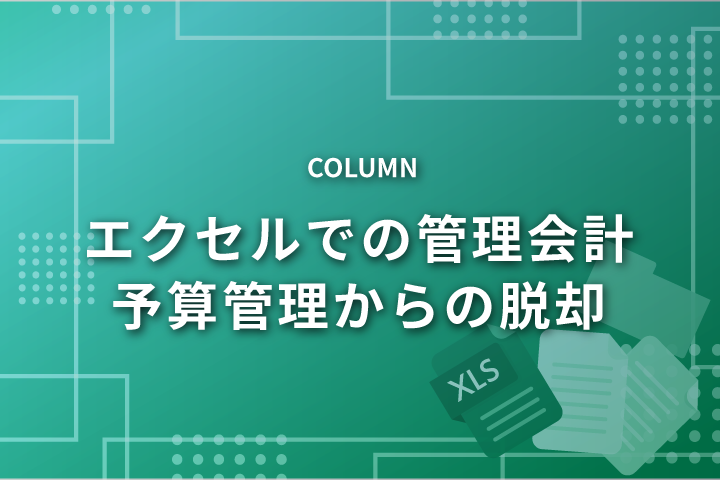
皆様、こんにちは。
「エクセルでの管理会計・予算管理からの脱却」というテーマでコラムを連載しております管理会計コンサルティング部の髙橋です。今回で3回目となります。
5月もすでに中旬を過ぎようとしていますが皆様GWはいかがでしたでしょうか。私はGWの初日に久しぶりに温泉に行ってきました。私自身一人暮らしのため、普段はシャワーを浴びることがほとんどのため、ゆっくりとお湯につかるのがとても久しぶりでした。日々の疲れを取る、とても良いリフレッシュになりました。
さて、今回は予算管理とクラウドサービスの親和性についてお話しさせていただきます。
予算管理はその特性上、クラウドサービスとの親和性が非常に高いと考えています。
※今回のコラムで扱うクラウドサービスは、予算管理のサービスをクラウド形式で提供するSaaSタイプのクラウドサービスのことを指します。
『費用面』における予算管理とクラウドサービス
まずは費用面についてです。予算管理という業務の必要性・重要性については今や語るべくもなく、ほぼすべての企業が行っているのではないでしょうか。しかし、予算管理業務の高度化・効率化に優先的に投資をする企業は決して多くはありません。実際私が営業活動を行っている中でも、製品自体は気に入っていただけるがなかなか予算が確保できないため見送りとなるケースが多々あります。
では予算管理の重要性は把握しているにも関わらず、企業としての投資の優先順位が低い原因はなんだと思いますか。
私は予算管理業務にお金をかけることによる投資対効果(ROI)の算出が難しいことが大きな原因になっていると思います。企業のメイン事業を支える基幹システムとは違い、日々の予算管理の結果は短期的な業績という数値にはなかなか反映されません。そのため企業としては高い予算を取ってまで新しいシステムを導入することに消極的になってしまいます。もちろん経営企画部や経理部などの業務負荷を下げるという意味では短期的にみても大きな効果を生みますがそれだけではもう一歩足りないと考えている企業が多いかと思います。つまり予算管理システムには業務の高度化・効率化はもちろん、「安価であること」が非常に重要視されます。
では「安価であること」が重要視される予算管理システムとクラウドサービスがなぜ親和性が高いと言われるのでしょうか。
まずクラウドサービスの大きな特徴として資産の購入・管理が不要ということが挙げられます。オンプレミスで予算管理システムを構築する場合、サーバの購入費用と購入後のサーバ維持費がランニングコストとして発生します。また、製品やサーバにアップデートの必要性が生じた場合、その都度SI費用が発生します。それに対してクラウドサービスではユーザ数毎に決められた使用料を払うのみとなります。そのため非常に安価に運用を始めることができます。
また、クラウドサービスとオンプレミス製品では、そもそものビジネスモデルの違いにより価格設定が異なります。オンプレミス製品の場合は基本的に売り切りのため、それ相応の価格で売られます。しかしクラウドサービスは契約していただくことで継続的に売上が立つため、まずは安価でも契約していただき、システムの成熟とともにライセンス数を広げていくという狙いがあります。そのため基本の価格設定はオンプレミス製品と比べて安価な傾向にあります。
『運用面』における予算管理とクラウドサービス
次に運用面についてです。予算管理業務では基本的に未来の数値を扱うことになるため、勘定科目や組織の構成が必ずしも現状のものと一致するとは限りません。来年度の予算を立てる際には、組織やその他セグメントを来年度用のものに切り替える必要があります。そのため実績を管理するERPシステムと比較すると科目のメンテナンスが頻発し、予算を管理する部門(経営企画部、経理部など)である程度柔軟に変更する必要があります。
また、予算管理はイベントのサイクル(四半期見直し、月次予測など)が早いため、システムの入れ替えを行う際にはそのイベントの間を縫って短期間での実施が求められる傾向にあります。
では「担当者による柔軟な運用」「短期導入」が重要視される予算管理システムとクラウドサービスがなぜ親和性が高いと言われるのでしょうか。
前項でもお話ししまたが、クラウドサービスではサーバを自社で持たないためシステムを管理するにあたってインフラ周りの知識が不要になります。そのためシステムを管理するにあたりSIerやIT部門を介さず、予算管理の担当者レベル(経営企画部、経理部など)で運用していくサービスモデルが多い傾向にあります。
これは弊社が用意している導入メニューに関しても同様です。基本的には弊社でサービス導入に必要な初期設計と初期構築、製品の使い方に関するユーザ教育を行い、実際の実装作業はお客様に行ってもらうようなメニューが中心となっています。そのためクラウドサービスにおける予算管理は「スモールスタート」が一般的な傾向であり、「担当者による柔軟な運用」「短期導入」が非常に実現しやすくなっています。
予算管理製品(クラウドサービス)のご紹介
次回は弊社が特に力を入れて扱っている以下の製品について実際に触れての感想を交えて特徴をご紹介したいと思います。
- Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS)
- Adaptive Planning
- Anaplan
予算管理業務の改善を検討されている担当者様はもちろん、予算管理やクラウドサービスという分野に興味がある方にも必見の内容となります。どうぞお楽しみに。